「手帳は書いているけど、満足して見返していない…」
「過去に何を書いたか探せず、結局ただの記録になっている…」
こんにちは。
新しい手帳を買ったときの、あのワクワク感。最初の数ページに、丁寧に目標や日々のタスクを書き込む作業は、それ自体がとても充実感のあるものですよね。
ですが、手帳術を実践しようとする多くの人が、この「書きっぱなし」という、静かですが非常に強力なワナに陥ってしまいます。
何を隠そう、私自身がその「ワナ」の常習犯でした。
年末になると本棚に並ぶ、分厚くなった手帳たち。それらは「書いた」という事実だけで満足してしまった、美しい「記録帳」のコレクションでした。まるで、未来に活かされることのない「手帳の墓場」を作っているようで、ある日、ふと虚しくなってしまったのを覚えています。
でも、心のどこかでは分かっていたんです。
手帳は「書くこと」がゴールじゃない。書いたことを「見返して未来に活かす」ための、人生の最強の相棒になるべきツールなんだ、と。
とはいえ、「忙しくて時間がない」「見返しても反省ばかりで辛い」「そもそも、開くこと自体が面倒くさい」…そのお気持ち、痛いほどよく分かります。私も、何度も何度も挫折してきましたから。
この記事では、そうした「見返すのが面倒」という根深い悩みを根本から解決し、あなたの大切な手帳を「未来を変える最強の相棒」に変えるための、具体的な「仕組みづくり」を、私の失敗談も交えながら、徹底的に深掘りしてご紹介します。
難しい根性論は一切ありません。「ああ、それならできそう」「そこまで考えていいんだ」と思えるヒントを、これでもかというほど詰め込みました。
「手帳術で見返す習慣」を本気で身につけたい。そう願うあなたのための、ステップバイステップガイドです。
この記事のポイント
- 手帳を見返す最大のメリットは「未来の行動を具体的に変える」こと
- 「書きっぱなし」はインデックスと記号(キー)を使った書き方で解決
- 振り返りは「できたこと」(ポジティブチェック)から見てネガティブ感情をなくす
- 「5分だけ」「週末だけ」など時間とタイミングを「仕組み」として固定する
- 「ふーん」で終わらせず「なぜ?」「どうする?」という問いで「次にやること(Next Action)」を必ず書く
- レビュー(振り返り)は「KPT法」など具体的なフレームワークを使うと迷わない
- 挫折しても大丈夫、完璧を目指さず「再開できる仕組み」が一番大事
なぜあなたは手帳を見返せない? 3つの「書きっぱなし」原因

「よし、今度こそ見返す習慣を身につけるぞ!」
そう固く決意しても、なぜか三日坊主で終わってしまう…。
何度も言いますが、それはあなたの意志が弱いからでは決してありません。多くの場合、「見返す」という行動には、私たちが思っている以上に強力な「心理的なブレーキ」がかかっているからです。
まずはそのブレーキの正体を、一緒に、じっくりと特定していきましょう。なぜ私たちは、あれほど大切に使い始めたはずの手帳を、開かなくなってしまうのでしょうか。
原因1:「忙しくて時間がない」「面倒くさい」(心理的ハードル)
これが最も一般的で、そして最も強力なブレーキかもしれませんね。
一日の終わりに、仕事や家事で疲れ果ててソファに倒れ込む。「さあ、今から手帳を振り返るぞ!」というエネルギーが、もう残っていない…。これは、人間として、とても自然なことです。
問題なのは、私たちが「手帳を見返す」という行為を、無意識のうちに「非常に大変で、エネルギーを使う作業」だと捉えてしまっていることです。
「見返すなら、ちゃんと1時間くらいかけて、コーヒーでも淹れて、じっくりと反省しないといけない」
「やるからには、完璧な振り返りをしなくては意味がない」
そんなふうに、完璧主義な自分(私の中では「完璧主義の校長先生」と呼んでいます)が、勝手にハードルを天井知らずに上げてしまっているのです。
私自身も、「週末にまとめてやろう」と先延ばしにした結果、その「週末」が来ても、今度は「ああ、1週間分も溜まってる…面倒だ…」と、さらに先延ばしにする…という負のループに陥った経験が何度もあります。
「少しでもいい」と思えない。「完璧にできないなら、ゼロのほうがマシ」という思考が、この「面倒くさい」の正体なのです。
原因2:「どこに何を書いたか分からない」(検索性の問題)
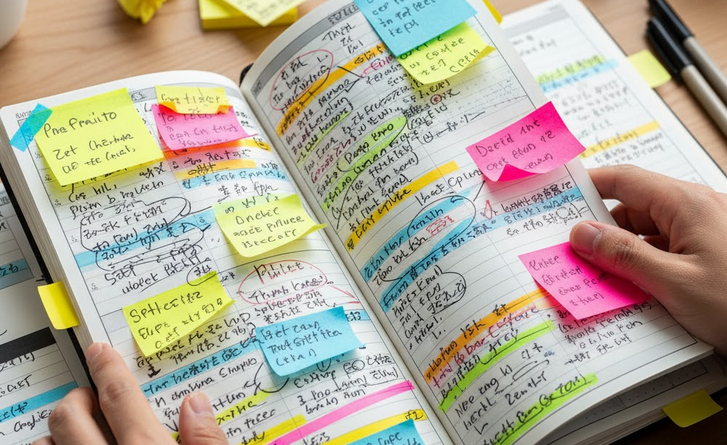
これは、手帳が「ただのメモ帳」になってしまっている場合に、確実と言っていいほど起こります。手帳を「混沌とした引き出し」にしてしまっている状態ですね。
- 「あの会議の重要なメモ、どこに書いたっけ?先週だったかな…」
- 「3週間前に思いついた、あの素晴らしいアイデアは…あれ、どのページだ?」
- 「読書メモと、買い物リストと、今日のタスクと、ふと感じた愚痴が、全部同じページにごちゃ混ぜになっている…」
想像してみてください。大切な書類を探しているのに、開けた引き出しの中が、古いレシートと、壊れたペンと、輪ゴムと、どうでもいいチラシで溢れかえっていたら…。
脳はそれを見た瞬間に「探すのが面倒だ」と判断し、無駄なエネルギーを使わないよう、そっと引き出しを閉じてしまいます。
手帳もまったく同じです。
私にも苦い経験があります。あるプロジェクトの画期的な改善案を、移動中の電車で手帳に殴り書きしたことがありました。しかし数週間後、そのアイデアが必要になった時、どのページに書いたかまったく見つけ出せなかったのです。パラパラとページをめくるうちに、「探す」こと自体に疲れ果ててしまい、結局そのアイデアは使われませんでした。
いくら素晴らしいことを書いても、必要な時にそれを見つけ出せなければ、その情報は「存在しない」のと同じです。探す手間に見合う「ご褒美(=情報発見)」が得られないと脳が学習してしまうと、もう見返すモチベーションは湧かなくなってしまいます。
原因3:「反省ばかりでネガティブになる」(感情的ハードル)
これは、真面目で、誠実で、一生懸命な人ほど陥りやすい、とても切実で、根深いワナです。
手帳を開く。
そこには、赤ペンで未完了のまま残された、ズラッと並んだ「できなかったタスク」のリストが…。
「ああ、これもできなかった」
「あれも中途半端だ」
「また目標達成できなかった…」
そんなふうに、「できなかったこと(=減点)」ばかりが目に飛び込んできて、自己嫌悪に陥ってしまう。
手帳は、本来なら自分を励まし、応援してくれるサポーターであるはずなのに、いつの間にか「自分のダメな部分を容赦なく突きつけてくる、厳しい監視役」になってしまうのです。
私の中には、かつて「赤ペン先生」と呼んでいた内なる批評家がいました。手帳を見返すたびに、この赤ペン先生が「ここがダメ」「あれが足りない」と厳しく指摘してくるのです。
見返すたびに「はぁ…」とため息が出るような手帳は、次第に開くこと自体がストレスになります。「これを見るくらいなら、SNSで楽しい動画でも見ていたほうがマシだ」と思ってしまうのは、これ以上傷つきたくない、自分を守るための当然の防衛反応だったんですね。
ステップ1:「見返す」を前提とした手帳の「書き方」

さて、3つの強力なブレーキ(原因)が見えてきました。
「心理的ハードル」「検索性の問題」「感情的ハードル」。
これらの問題を解決するために、まず私たちが変えるべきは「根性」や「やる気」といった曖昧なものではありません。
「書き方」そのものです。
「どうせ未来の自分が見返すんだから」という前提に立って、未来の自分が「うわ、見返しやすい!ありがとう、過去の私!」と喜ぶような書き方を、今から仕込んでおきましょう。
「探す手間」をゼロにし、ネガティブな感情を抱かせない。ストレスなく情報にアクセスできるフォーマットを作ることが、すべての始まりです。
「検索性」を劇的に上げるインデックス(目次)活用術
「どこに何を書いたか分からない」(=混沌とした引き出し)問題を、一発で、劇的に解決するのが、「インデックス(目次)」です。
これは、高価なシステム手帳でなくても、1冊のノートで手帳術を実践している(いわゆるバレットジャーナル)方にも使える、非常に強力なテクニックです。
やり方は驚くほど簡単です。
- 手帳(ノート)の最初のページを2〜4ページほど、白紙のまま空けておきます。ここが「インデックス」専用ページになります。
- 手帳の各ページに、ページ番号(ノンブル)を振っておきます。(最初から振られている手帳なら、そのままでOK。なければ、自分で書き込みましょう)
- 今後、何か「これは後で絶対に見返すな」という「まとまった情報」を書いたら(書いた直後に、がポイントです)、インデックスページに戻り、ページ番号とタイトルを書き込みます。
(インデックスページの例)
2025年の目標リスト …………… p5〇〇研修のメモ ………………… p18-21△△プロジェクト議事録 ……… p25, p32, p45「続ける」技術 読書メモ …… p38心に残った言葉集 …………… p40-(続く場合)子供の成長記録 2025 ……… p50Webサイト改善アイデア集 …… p55
たったこれだけです。
「インデックスを作る」という作業自体が面倒に感じるかもしれませんが、これは未来の自分への「投資」です。
私自身、これを始めてから手帳の価値が10倍になりました。
「あの時の会議の決定事項、何だっけ?」→ インデックスを見る →「p32だ!」
「半年前の目標、どう立ててたっけ?」→ インデックスを見る →「p5だ!」
あなたの手帳は「ただのメモの束」から、「自分だけのオリジナル参考書」に進化します。「あのメモどこだっけ?」とイライラしながらページをパラパラ探す時間がゼロになり、「見返す」ことへの心理的抵抗が劇的に下がりますよ。
記号(キー)を使ってメモを瞬時に分類する
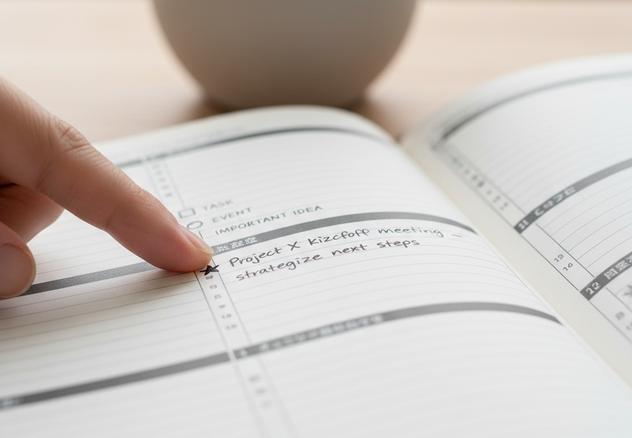
次に、「ごちゃ混ぜ」問題を解決します。
インデックスが「まとまった情報」を探すためのものなら、こちらは「日々の細かな情報」を分類するためのテクニックです。
これは、バレットジャーナルで使われる「キー(Key)」という考え方を、自分なりにシンプルに応用したものです。
手帳に書き込む内容を、あらかじめ簡単な「記号」で分類してしまいます。
(私の基本キーの例)
・(中黒) : メモ、出来事、気づき(ただの記録)□(四角) : タスク(今日やること)〇(丸) : 完了したタスク(□に上書きしてもOK)!(感嘆符): アイデア、ひらめき(重要!)→(矢印) : 先送りしたタスク、転記したメモ?(疑問符): あとで調べること、疑問☆(星) : 嬉しかったこと、ポジティブな出来事
これを、書き込む文章の先頭につけるだけです。
(手帳の1ページの例)
10月24日(金)
・ 〇〇さんとランチミーティング。とても有意義だった。
□ スーパーで牛乳と卵を買う
? 来週のプレゼン資料のA案、B案のメリットを整理する
! ブログの新企画「手帳の見返し方」を思いついた。読者の悩みを3つに分類する。
☆ 息子が初めて自転車に乗れた!
これの何がそんなに良いのでしょうか?
それは、見返す時に「拾い読み」ができることです。
例えば、週末の週次レビューの時。
「今週の未完了タスクだけチェックしたい」と思ったら、□(四角)や→(矢印)の記号がついている行だけを、サーっと目で追えばいいのです。
「今週の『良かったこと』を集めたい」なら、☆(星)の記号だけを探す。
「アイデアだけ見返したい」なら、!の記号だけを探す。
すべての文章を律儀に、真面目に読み返す必要がなくなるのです。
これにより、「見返す」スピードと効率が格段にアップします。これは、「完璧主義」で全部読もうとして疲れてしまう、真面目な人(かつての私です)にこそ試してほしいテクニックです。
※コツは、キーを増やしすぎないこと。自分がパッと見て分かる、5〜7個程度に絞るのがおすすめです。
「未来の自分」への引継ぎ欄を作る
これは、日々の「書きっぱなし」をなくすための、小さな、しかし非常に強力な「仕掛け」です。
デイリーページやウィークリーページの最後に、「引継ぎ欄」とでも呼べるような小さなスペースをあらかじめ作っておきます。(私は「→Next」と書いて枠で囲っているだけです)
そして、その日の最後に(あるいは、書く作業が終わった時に)、未来の自分自身に「引継ぎメモ」を残すのです。
- 「このタスクは明日へ
→」 - 「このアイデアは
p55のアイデア集へ転記」 - 「この反省(
?)は、週末のレビューでじっくり考える」 - 「〇〇さんへの返信、明日必ず!」
これは、未来の自分への「申し送り事項」です。
これを書いておくだけで、見返した時に「ふーん」で終わるのを防げます。「あ、このページを見返した私は、これをやればいいんだな」と、次の行動が明確になるからです。
「過去の自分」が、「未来の自分」の仕事(=見返す作業)を少しだけ手伝ってあげる。この「時空を超えたチームプレー」が、見返す習慣を強力にサポートしてくれます。
ステップ2:「いつ・何を」見返す? 振り返り習慣化システム

さて、ステップ1で「書き方」が整い、あなたの手帳は「非常に見返しやすい」状態になりました。
これで「検索性の問題」と、ある程度の「心理的ハードル」はクリアできたはずです。
いよいよ、このセクションのテーマである「手帳術 見返す 習慣」の核となる部分、「習慣化」の仕組みづくりに入ります。
「いつか見返そう」は、残念ながら永遠にやってきません。
なぜなら、私たちの脳は「緊急ではないが重要なこと」を後回しにする天才だからです。
だからこそ、「いつ」「何を」見るかを具体的に決めてしまう「仕組み(システム)」 が必要なのです。
それはまるで、歯磨きや入浴のように、生活のルーティンに「予約席」を作ってあげるイメージです。
ここでは、現実的に継続可能な3つの「レビュー(振り返り)システム」を、その「目的」と共に詳しくご紹介します。
「毎日5分」の夜レビュー(タスクの棚卸し)
目的: その日のタスクを「完了」させ、頭の中を空っぽにして安心して眠るため。
タイミング: 寝る前、または仕事が終わった直後。(「パジャマに着替えたら」など、具体的な行動とセットにするのがおすすめです)
見返すページ: 今日のデイリーページ(またはウィークリーページ)
やること(たったの5分です):
- タスクの棚卸し:
- 今日完了したタスク(
□)に、お気に入りのペンで完了マーク(〇や✔)をつける。 - 今日できなかったタスク(
□)を見る。 - 「明日やるか」「週末に回すか」「そもそも、もうやらなくていいか」を冷静に判断する。「明日やる」と決めたタスクは、明日のページに→(矢印)をつけて転記する。(「引継ぎ」の実践です)
- 今日完了したタスク(
- (余裕があれば)一言メモ: 今日の「良かったこと(
☆)」や「感謝」を一つだけ書く。
効果:
この5分レビューの最大の効果は、「タスク漏れを防ぐ」こと、そして「頭の中を空っぽにする」ことです。
私たちが不安になるのは、「何か忘れていることがあるんじゃないか」という曖昧な感覚がある時です。
「あれ、明日やるべきことなんだっけ?」と考えながらベッドに入るのではなく、「全部手帳に書き出した。今日の私は、ここまで」と、脳に「シャットダウン」の合図を送る儀式です。
たった5分ですが、この「脳のシャットダウン儀式」は、睡眠の質を高め、精神衛生を劇的に改善してくれます。
「週末30分」の週次レビュー(軌道修正)

これこそが、「手帳を未来に活かす」ための最重要レビューです。
もし「毎日5分」が難しくても、これだけは、これだけはぜひ実践してほしいと心から願っています。
目的: 1週間の経験(データ)を分析し、次の1週間の行動を「より良く」軌道修正するため。
タイミング: 金曜の夜、または日曜の夜など、週に一度、30分だけ落ち着ける時間。「このカフェに入ったらやる」「お風呂から上がったらやる」など、場所や行動とセットにします。
やること(この「順番」が命です!):
- 【最重要】ステップ1:ポジティブチェック(宝探し)まずは、お気に入りの色のマーカー(私は幸せな気分の黄色を使います)を持って、今週のページをパラパラと読み返します。そして、「できたこと」「嬉しかったこと」「楽しかったこと(☆)」に、どんどん印をつけていきます。
- 「朝、5分早く起きられた」
- 「〇〇さんに『ありがとう』と言えた」
- 「ランチのパスタが最高に美味しかった」
- 「タスクを3つ完了できた」どんなに小さなことでも構いません。これは「反省」ではなく「宝探し」です。
- 【次に】ステップ2:現状把握(データ分析)次に、別の色のマーカー(私は冷静になれる青を使います)で、「できなかったこと(□)」「問題点」「気になったメモ(?)」に印をつけます。※注意点: ここで「ああ、ダメだ」と落ち込まないこと。ステップ1で自分の「できたこと」を確認しているので、少し強気になれているはずです。「ほう、こんなデータが出たか」と、自分を客観的に分析する「アナリスト」の視点で印をつけます。
- 【最後に】ステップ3:未来への転換(戦略会議)印をつけた項目(特に青マーカー)を見ながら、新しいページ(来週のページや、週次レビュー専用ページ)に、「来週やること(Next Action)」を書き出します。ここで役立つのが、「KPT(ケプト)法」 というシンプルなフレームワークです。
- K (Keep): 良かったこと、来週も「続けたい」こと。(黄マーカーから抽出)
- P (Problem): 問題点、今週「やめたい」こと。(青マーカーから抽出)
- T (Try): Problemを解決するために、来週「新しく試す」こと。(=Next Action)
効果:
ステップ1の「ポジティブチェック」を最初に行うことで、「原因3:ネガティブになる」を根本から防ぎます。「私、今週も色々あったけど、結構頑張ったじゃないか」という自己肯定感が、レビューの土台になります。
その上で、「じゃあ、来週はどうしよう?」と前向きに軌道修正ができるようになります。これが、手帳を使った「成長のサイクル(PDCAのCとA)」そのものなのです。
「月末1時間」の月次レビュー(目標の再設定)
これは、日々のタスクという「木」ではなく、人生の目標という「森」を見るための、少し視野を広げたレビューです。
目的: 1ヶ月のパターンを把握し、長期的な目標を再設定・確認するため。
タイミング: 月末の週末など。少しリッチなカフェで、自分と「お疲れ様会」を開くのも素敵ですね。
やること:
- インデックス(目次)の確認: 今月、自分はどんな「まとまった情報」をインデックスに追加したか(読書、プロジェクト等)を眺めます。
- 週次レビューの「T (Try)」の確認: 4回分の週次レビューページを見返し、「試す」と決めたことが、どれだけ実行できたか、その結果どうだったかを見ます。
- パターンの発見:
- 「あれ、毎月第3週は必ず体調を崩してるな…」(→来月は第3週の予定を減らそう)
- 「『!』(アイデア)が、なぜか水曜の午前中に集中している」(→水曜午前はアイデア出しの時間にしよう)
- 「今月は『☆』(ポジティブ)が少なかったな。なぜだろう?」(→来月は意識的に楽しい予定を入れよう)
- 目標の再設定: それらを踏まえて、「来月の目標」や「来月やりたいことリスト」を、新しいページに具体的に書き出します。
効果:
「ただ忙しく働いたけど、結局何が進んだんだろう?」という焦燥感をなくし、「自分はちゃんとデータに基づいて、前に進んでいる」という長期的な視点と、人生の「舵」を自分で握っている感覚を持つことができます。
「ふーん」で終わらせない!見返した情報を「行動」に変えるコツ
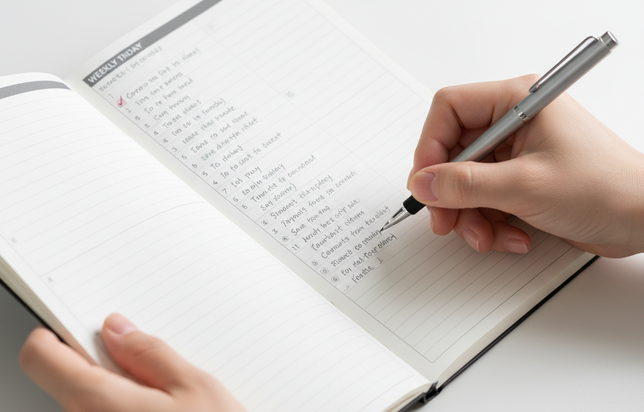
さて、仕組みは整いました。ステップ1で書き方を、ステップ2で習慣化システムを作りました。
最後の仕上げは、「見返す」という行為の「質」を、もう一段階、二段階と高めるための具体的なコツです。
見返した時に、「ふーん、こんなことあったな」と、ただ過去を懐かしむ(=ただの思い出)で終わらせては、手帳のパワーを半分も使えていません。
見返す目的は、あくまで**「未来の行動を変える」**ことです。
「過去のデータ」を「未来の戦略」に変える、具体的な思考法を3つご紹介します。
「できたこと」から見返す(ネガティブ防止)
これは週次レビューでも触れましたが、あまりに、あまりに重要なので、何度でも言わせてください。
どうか、手帳を開いていきなり「できなかったこと」を探すのは、今日からやめてみてください。
私自身、かつては「できなかったタスク」を赤ペンでチェックする癖があり、それが振り返りを「減点法」の憂鬱な時間にしていました。
脳は、ポジティブな感情(報酬)があると、その行動を「快」と認識し、習慣化しやすくなります。
「手帳を開く=自分の頑張りを認めてもらえる、嬉しい時間」
この関連付けを作ることが、何よりも大切です。
「今日もできた」「これもできた」と、自分に小さな「花マル」をあげる時間として、手帳を使ってみてください。振り返りは「反省会」ではなく、「自分お疲れ様会」であり、「宝探し」の時間なのです。
「なぜ?」を問いかけ、次のアクションを「書く」
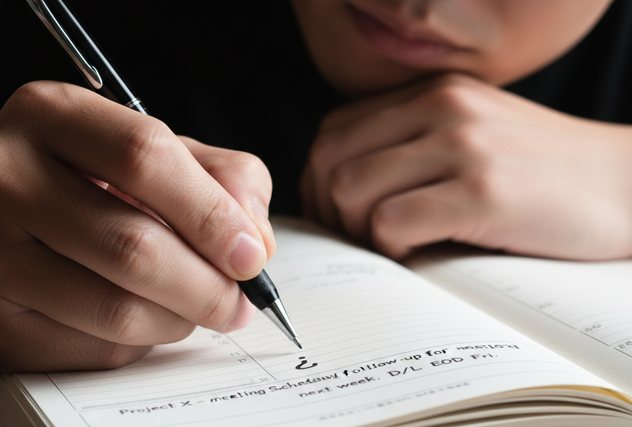
「ふーん」で終わらせないための、魔法の質問。それは**「なぜ?」と「どうする?」**です。
これは、トヨタ生産方式で有名な「なぜなぜ分析(5 Whys)」の簡易版です。
一つの事象に対して、「なぜ?」を問いかけ、表面的な理由ではなく、根本的な原因(真因)を探る思考法です。
- (例1)「このタスクが今週も終わらなかった」
- → なぜ? → 「見積もりが甘かった。思ったより時間がかかる作業だった」
- → (さらに)なぜ? → 「途中で何度もメールチェックをして、集中が途切れたからだ」
- → どうする?(Next Action) → 「来週は『ポモドーロ・テクニック(25分集中+5分休憩)』を使う。その間はメールソフトを閉じる」
- (例2)「イライラして家族に当たってしまった」
- → なぜ? → 「仕事のプレッシャーと寝不足が重なっていた」
- → (さらに)なぜ? → 「寝る前にスマホで仕事のメールを見てしまい、脳が興奮して寝付けなかったからだ」
- → どうする?(Next Action) → 「夜10時以降はスマホをリビングで充電する。寝室に持ち込まない」
この「どうする?(Next Action)」の部分こそが、あなたの手帳が未来のあなたに渡すべき、最も価値のある「処方箋」です。
これを「書く」までが、ワンセットの「見返し」です。
見返した情報を「新しいページ」に転記・集約する
最後のコツは、非常に物理的ですが、驚くほど効果的なテクニックです。
せっかく見返して「どうする?」(=Next Action)を決めても、その情報が「過去」のページ(先週のページ)に書かれたままでは、絶対に忘れます。
なぜなら、私たちは未来のページしか日常的には見ないからです。
週次レビューや月次レビューで得られた「気づき」や「次のタスク」は、過去のページに残さず、
必ず「今週のページ」「来月の目標ページ」「タスクリスト」など、これから何度も目にする「未来のページ」に、自分の手で書き写す(転記する)ようにしてください。
この「転記」という物理的な作業が、
「ああ、私はこれをやるんだな」
と、脳に強くインプットする効果も生みます。
これが、過去の経験を未来の行動に直結させる、最も確実な「引継ぎ」作業となります。
それでも続かない…「見返す習慣」挫折あるあるQ&A
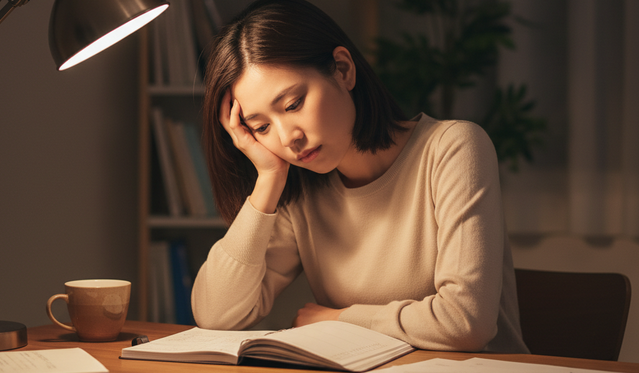
ここまで、かなり具体的な仕組み(システム)についてお話してきました。
でも、きっとこう思う方もいらっしゃるでしょう。
「理屈は分かった。でも、それができれば苦労しないんだよ…」
その気持ちも、本当によく分かります。
仕組みを作っても、私たちは人間ですから、必ず「できない日」がやってきます。
最後に、そんな「挫折あるある」の悩みにお答えするQ&Aコーナーを設けました。
Q1. 週末にレビューを忘れてしまいました。もうダメですか?
A1. まったくダメではありません!「ゼロか100か」思考を捨てましょう。
これが「完璧主義」の最大のワナです。「一度できなかった=すべてが終わり」と感じてしまうのです。
でも、大切なのは「完璧に続けること」ではなく、「途切れても、また再開すること」 です。
週末に忘れたら、月曜の朝に10分だけやればいいのです。それも無理なら、火曜でもいい。1週間分が無理なら、「ポジティブチェック(宝探し)」だけでもいい。
「ゼロ」にするくらいなら、「10」でも「1」でもいいから「やる」こと。
手帳術は、自分を縛る「ルール」ではなく、自分を助ける「ツール」であることを忘れないでください。
Q2. 毎日5分すら時間が取れません。どうすれば?

A2. 「時間」ではなく「タイミング」に注目してください。
「5分」という時間を確保しようとすると難しく感じますが、特定の「行動」にくっつけると習慣化しやすくなります。これを「トリガー」と呼びます。
- 歯を磨きながら、開いた手帳を眺める(書かなくてもOK)
- トイレに座ったら、1分だけタスクチェックする
- 電車で席に座ったら、まず手帳を開く
「頑張って時間を捻出する」のではなく、「どうせやる行動」に「ついでに」組み込んでしまうのがコツです。
Q3. デジタル(カレンダー)とアナログ(手帳)、どう見返せばいい?
A3. それぞれの「得意分野」で役割分担させましょう。
デジタルとアナログの併用は、現代人にとって大きなテーマですよね。私の場合は、以下のように役割分担しています。
- デジタル(Googleカレンダーなど):
- 役割: 他人と共有する「確定した予定(アポイント)」の管理。
- 見返し方: 「確定した未来のスケジュール」として、日次・週次で確認する。
- アナログ(手帳):
- 役割: 「自分との対話」。タスク、アイデア、反省、感情、KPTなど。
- 見返し方: 記事で紹介した「日次・週次・月次レビュー」で、じっくりと「過去のデータ」として分析する。
デジタルは「未来の確定事項」、アナログは「過去の分析と未来の戦略」と分けると、頭がスッキリしますよ。
見返す習慣が自然につく手帳術まとめ

手帳の「見返す習慣」を身につけることは、単なるタスク管理術ではありません。
それは、他の誰でもない、「過去の自分」という世界で唯一の、最高の教材から学び、自分だけの成功パターンや失敗パターンを分析し、「未来の自分」を少しずつ、確実に成長させていくための、最強の自己投資です。
「書きっぱなし」で、せっかくの教材を、あなたの貴重な「経験のデータ」を埃まみれにしておくのは、あまりにも、あまりにもったいない。
ご紹介したテクニックは、どれも小さなものばかりです。
でも、小さな一歩こそが、未来を変える唯一の道です。完璧を目指さず、「これならできそう」というもの一つから、ぜひ試してみてください。
あなたの手帳は、あなたが思っている以上に、未来を変えるヒントで溢れています。
まとめ
- 「書きっぱなし」は「面倒」だからではなく「仕組み」がないから
- 「インデックス(目次)」と「記号(キー)」で見返す前提の書き方にする
- 「できたこと(ポジティブ)」から見返してネガティブな感情をなくす
- 「夜5分」「週末30分」など時間を決めて「仕組み」化する
- 「KPT法」や「なぜなぜ分析」で見返しを「未来の戦略」に変える
- 見返しは「次にやること(Next Action)」を「未来のページ」に書くまでがセット
- 完璧を目指さない、途切れても「再開」できることが一番大事
- 過去の自分は「反省対象」ではなく「最高の教材」
