「この記事、頑張って書いたのに全然読まれない…」
「もしかして、自分のブログタイトルってセンスない…?」
こんにちは!長年ブログという世界で言葉を紡いできた筆者です。今でこそ、多くの方に「記事、読んでます!」と温かい言葉をかけていただけるようになりましたが、ほんの数年前まで、私もあなたと全く同じ暗闇の中で、一人膝を抱えていました。
忘れもしません。ブログを始めて半年が経った頃、丸三日を費やして書き上げた渾身の記事がありました。データも徹底的に調べ、写真も何十枚と撮り直し、自分でも「これは多くの人の役に立つはずだ!」と確信していたのです。しかし、公開後一週間のアクセス数は「17」。そのほとんどは、きっと自分自身で確認したアクセスでした。
あの時の絶望感と無力感は、今でも胸が締め付けられるように思い出します。「自分の文章は、誰にも必要とされていないんじゃないか…」そんな風に、書くことへの情熱すら失いかけていました。
そんな時、ある恩人であるベテラン編集者から、こう言われたのです。
「君の記事は、素晴らしい料理だ。でも、そのお店には看板が出ていない。いや、出ていたとしても、薄汚れていて何のお店か分からない看板だ。これじゃあ、誰も扉を開けてはくれないよ」と。
頭をガツンと殴られたような衝撃でした。私は、記事の中身(料理)にばかりこだわって、読者が一番最初に目にする「タイトル(看板)」の重要性を、全く理解していなかったのです。
この記事でお伝えするのは、かつての私のように、素晴らしい情熱と才能を持っているにもかかわらず、タイトルの付け方一つで読者に届かずに悩んでいる、あなたへの手紙です。
2025年の今、多くの人が無意識にやってしまっている「ブログタイトルのダサい例」を、私自身の数々の失敗談も包み隠さずお話ししながら、具体的なビフォーアフターと共に徹底解説します。
この記事は、センスという曖昧なものではなく、「これだけは避けるべき」という明確なルールブックです。このルールブックを手にすることで、あなたはもう二度とタイトル決めで迷うことはなくなり、自信を持って自分の記事を世に送り出せるようになります。ぜひ、最後までじっくりと、お付き合いください。
-
多くの人が陥る「ダサいタイトル」の具体的な失敗パターンを10個提示
-
なぜそのタイトルが読者にスルーされるのか、その心理を解説
-
ダサいタイトルを魅力的に変える改善テクニックをビフォーアフターで紹介
-
記号や定番フォーマットの現代的な使い方を解説
-
今後のタイトル決めで使える明確なNGルールとチェックリストを提供
-
さらに一歩進んだ、読者の心を鷲掴みにする「神タイトル」の応用テクニックも公開
【2025年最新版】あなたのタイトルは大丈夫?やりがちな「ダサいブログタイトル」NG例10選

それでは早速、多くのブロガーが気づかずに使ってしまっている「ダサいタイトル」の具体的なパターンを10個、改善例とセットでご紹介します。まるで健康診断を受けるような気持ちで、ご自身の過去記事と答え合わせをしながら読み進めてみてください。一つ一つのパターンに、私たちが陥りがちな心理的な罠が隠されています。
パターン1:【必見!】記号と感嘆符だらけの「過剰装飾」タイトル
【ダサい例】
【必見!】絶対やるべき!ブログで稼ぐためのスゴい裏技教えます!!
【改善例A(シンプルに)】
ブログ収益化の鍵は記事タイトルにあった。月1万円を達成したシンプルな裏技3選
【改善例B(ターゲットを絞る)】
《ブログ初心者向け》「必見」や「スゴい」を使わずにクリック率を2倍にしたタイトル術
【解説】
2010年代のブログ文化では、目を引くために記号を多用するスタイルが流行しました。しかし、情報過多の現代において、読者の目は肥えています。過度な記号や感嘆符は、心理学でいう「認知負荷」を高め、「読むのが疲れそう」「なんだか胡散臭いな…」という無意識の抵抗感を生んでしまうのです。
これは、街中で派手なネオンをチカチカさせ、大音量で音楽を流しているお店に、かえって入りづらくなる心理と全く同じです。本当に価値のある情報、本当に美味しい料理を提供しているお店は、本来、落ち着いた佇まいの中に自信を宿しているものです。読者の信頼を勝ち取るためにも、記号は【】や《》などを1つだけ、記事のジャンルやターゲットを明確にするために戦略的に使いましょう。
【こんな記事で特に注意!】
収益化やノウハウ系の記事で、自信のなさを隠すために無意識に多用してしまいがちです。自信がある内容ほど、装飾はシンプルに。
パターン2:誰にも響かない「日記・ポエム風」タイトル
【ダサい例】
今日の出来事と、感じたこと。
【改善例A(学びを抽出)】
開店30分で完売する人気パン屋の行列に並び、学んだ3つの顧客心理
【改善例B(失敗談を価値に)】
【失敗談】初めての一人旅で私が犯した5つのミスと、その回避方法
【解説】
私自身もブログを始めたばかりの頃は、この罠にどっぷりと浸かっていました。「今日の夕焼けは綺麗だった」とか「〇〇を読んで感動した」とか、自分の中では大切な感情なのですが、読者から見ればそれは「知らない人の日記」でしかありません。
読者がGoogleの検索窓に言葉を打ち込むのは、自分の悩みや疑問を解決したいという、極めて実利的な動機があるからです。あなたの体験は、そのままだとただの日記ですが、「そこから得られた学び」や「読者の代わりに経験した失敗談」というフィルターを通すことで、初めて「読者のための価値ある情報」に昇華するのです。あなたの感動体験は、「読者が同じ感動を味わうためのガイド」として書き直すことができないか、常に自問自答してみましょう。
【こんな記事で特に注意!】
旅行ブログ、書評ブログ、学習記録ブログなど、個人の体験がベースになる記事で陥りがちです。常に「この体験は、読者の何の役に立つだろう?」と考える癖をつけましょう。
パターン3:中身が全く想像できない「意識高い系・横文字」タイトル
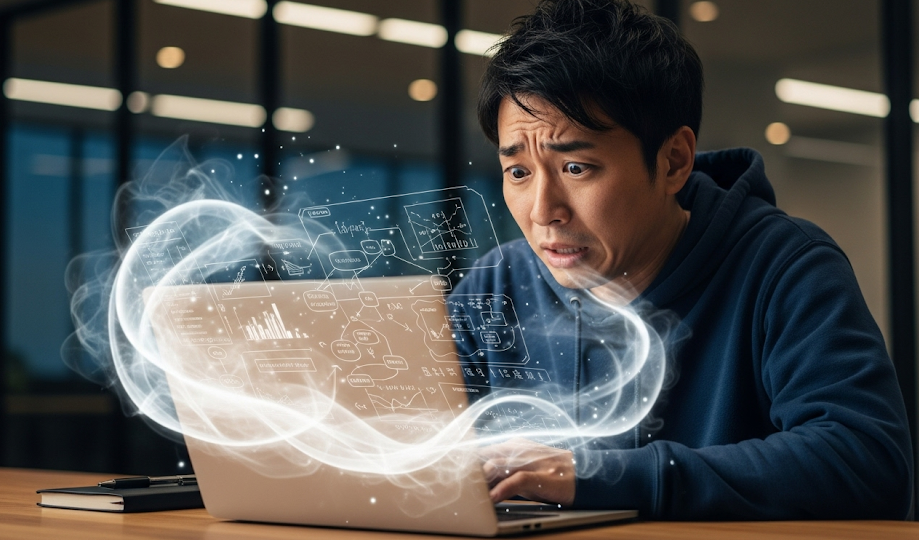
【ダサい例】
僕がコミットした、コンテンツマーケティングのパラダイムシフト
【改善例A(分かりやすく翻訳)】
「毎日更新」はもう古い。2025年にアクセスを伸ばすコンテンツ戦略とは
【改善例B(結果を提示)】
この思考法に切り替え、ブログの月間アクセス数が半年で5倍になった話
【解説】
専門用語やビジネス系のカタカナ言葉を並べると、一見すると専門性が高く見えるかもしれません。しかし、それは書き手の自己満足であり、読者との間に見えない壁を作ってしまいます。ほとんどの読者は、その分野の専門家ではありません。
このタイトルは、初めて訪れた高級レストランで、メニューが知らない外国語で書かれているようなものです。「美味しいものが食べたい」と思って来たのに、何を頼めば良いのか分からなければ、不安になってお店を出てしまいますよね。難しい言葉は記事の中で丁寧に解説するとして、タイトルでは小学生でも意味がわかるくらい、シンプルで噛み砕いた表現を心がけることが、読者への本当の「おもてなし」です。
【こんな記事で特に注意!】
ビジネス系、マーケティング系、テクノロジー系のブログで、つい専門性をアピールしたくて使ってしまいがちです。専門家こそ、分かりやすい言葉で語るべきです。
パターン4:時代遅れ感が漂う「古いネットスラング」タイトル
【ダサい例】
ブログのアクセスアップ術、キタ――(゚∀゚)――!! ワロタw
【改善例A(普遍的な言葉で)】
Googleアップデート後もアクセスを2.3倍にした、ブログSEOの本質的な対策
【改善例B(現代的な表現で)】
【SNSで話題】知らなきゃ損する、ブログのアクセスアップ術5選
【解説】
インターネットの世界の流行り廃りは、私たちが思っている以上に高速です。数年前に誰もが使っていた顔文字やネットスラングも、2025年の今となっては「なんだか古い…」「この書き手、いつの時代の人だろう?」という違和感を与えかねません。
これはファッションと同じで、どんなに素敵な人でも、10年前に流行った服を着ていたら、少しチグハグな印象を与えてしまいますよね。特に、情報の鮮度が重要なテーマを扱うブログであれば、言葉遣いの古さは記事全体の信頼性を損なう致命的な欠陥になり得ます。一過性の流行り言葉に頼るのではなく、時間が経っても色褪せない、丁寧で普遍的な言葉を選ぶことが、長く愛されるブログへの近道です。
【こんな記事で特に注意!】
エンタメ系やガジェット系のブログで、親しみやすさを出そうとして使いがち。親しみやすさと古臭さは紙一重です。
パターン5:読者不在の「自分語り・自慢」タイトル
【ダサい例】
私がブログで月収100万円を達成した話
【改善例A(再現性を示す)】
特別なスキルがなくても、ブログで月収10万円を稼ぐまでの具体的な6ステップ
【改善例B(読者のメリットを強調)】
月収100万円ブロガーが密かに実践している、収益を10倍にする記事構成術
【解説】
月収100万円という実績は、本当に素晴らしいものです。しかし、読者がそのタイトルから知りたいのは「あなたの自慢話」ではなく、「その素晴らしい結果を、自分も手に入れるための方法」です。タイトルが自慢話で終わってしまうと、読者は「すごいね(でも、この人だからできたんでしょ?)」と感じ、自分事として捉えることができません。
ここで大切なのが、「再現性」と「ノウハウの切り出し」です。改善例Aのように「特別なスキルがなくても」と加えることで、読者に希望を与えられます。改善例Bのように、素晴らしい結果の中から「読者が真似できるノウハウ」を切り出して提示することで、読者は初めて「この記事は、自分のために書かれている」と感じるのです。主語を「私」から「あなた(読者)」へと意識的に切り替えることが、共感を呼ぶタイトルの秘訣です。
【こんな記事で特に注意!】
実績報告や成功体験を語る記事。実績はあくまで読者の興味を引くフックであり、主役は「読者がどうなれるか」です。
パターン6:情報がゼロな「平凡・ありきたり」タイトル
【ダサい例】
京都旅行に行ってきた
【改善例A(ターゲットを絞る)】
【予算3万円】京都の定番を外した、通だけが知る穴場観光モデルコース
【改善例B(体験を切り出す)】
雨の京都も悪くない。三十三間堂で心が洗われた、静かな一人旅の記録
【解説】
このタイトルを見た読者の頭の中は「それで?」「どんな情報があるの?」という疑問符でいっぱいです。検索結果には、似たような「京都旅行に行ってきた」記事が何十個も並んでいます。その中で、あなたの記事を選んでもらう理由がどこにもありません。
平凡なタイトルを特別なものに変える魔法は、「具体性」と「独自性」です。「予算3万円」「穴場」といった具体的な数字やキーワードでターゲットを絞る。あるいは「雨の京都」「一人旅」といった、あなただけの体験から得られた独自の視点を切り出す。そうすることで、ありきたりなテーマが「まさに私が求めていた情報だ!」という、運命的な出会いに変わるのです。
【こんな記事で特に注意!】
旅行、グルメ、イベントレポートなど、多くの人が書くテーマの記事。他の記事との「違い」は何かを徹底的に考えましょう。
パターン7:使い古された「定番フォーマット乱用」タイトル
【ダサい例】
ブログの始め方3つのステップ
【改善例A(付加価値を加える)】
【2025年版】知識ゼロからでも失敗しない、WordPressブログの始め方総まとめ
【改善例B(切り口を変える)】
ブログ開設で初心者が躓く「サーバー契約」を、世界一分かりやすく解説します
【解説】
「〇〇な理由3選」「〇〇する方法5ステップ」といった定番の型は、内容が整理されていて読者に伝わりやすく、非常に有効なテクニックです。私自身も多用しています。しかし、あまりにも多くの人が使っているため、ただキーワードを入れ替えただけでは、スーパーの特売卵のように、その他大勢の中に埋もれてしまいます。
これも料理に例えるなら、「カレーライス」というメニューだけでは、他のたくさんのお店と差別化できません。「A5ランクの黒毛和牛を使った」「30種類のスパイスを独自ブレンドした」といった、独自のこだわりを付け加える必要があります。ブログタイトルも同様に、「2025年版」「失敗しない」「総まとめ」といった情報の網羅性や鮮度をアピールしたり、「サーバー契約」のようにテーマを極端に絞って専門性を高めたりと、他との差別化要素を加える工夫が不可欠です。
【こんな記事で特に注意!】
ノウハウ系の記事全般。競合記事のタイトルを10個以上見て、それらにはない独自の価値を加えられないか考えましょう。
パターン8:クリックを躊躇させる「ネガティブ・否定的」タイトル
【ダサい例】
ブログなんてやっても無駄。絶対に稼げない理由。
【改善例A(解決策を提示)】
9割の人がブログで稼げずに辞めていく理由と、残りの1割に入るための思考法
【改善例B(ポジティブに転換)】
「ブログは稼げない」は嘘。凡人が月5万円を稼ぐための超現実的なロードマップ
【解説】
強い否定やネガティブな言葉は、確かに人の目を引きます。心理学でいう「ネガティビティ・バイアス(人はポジティブな情報よりネガティブな情報に注意を向けやすい)」を利用したテクニックです。しかし、ただ不安を煽るだけで終わってしまうタイトルは、読後感が最悪で、あなたのブログのファンを遠ざけてしまいます。
重要なのは、問題提起とセットで「解決策」や「希望の光」を提示することです。改善例Aのように、厳しい現実を示しつつも、それを乗り越えるための方法も示唆する。改善例Bのように、一般的な否定論に反論し、ポジティブな未来への道筋を示す。そうすることで、読者は「この記事には、私の悩みを解決するヒントがありそうだ」と感じ、安心してクリックすることができるのです。
【こんな記事で特に注意!】
警鐘を鳴らすタイプの記事や、一般的な常識に物申す記事。読者を突き放すのではなく、寄り添い、導く姿勢が大切です。
パターン9:キーワードを詰め込みすぎた「SEO意識過剰」タイトル

【ダサい例】
ブログ タイトル 決め方 コツ SEO 文字数 おすすめ 2025年
【改善例A(自然な文章に)】
【SEO対策】ブログタイトルの最適な文字数は?2025年のクリック率を高める決め方のコツ
【改善例B(キーワードを絞る)】
ブログタイトルの決め方で悩む人へ。SEOより大切な「読者の心に刺さる」3つのコツ
【解説】
SEOを意識するあまり、検索されたいキーワードをただ並べただけのタイトル。これは、検索エンジンに評価される以前に、「読者」という最も大切な存在を無視してしまっています。ロボットが書いたような無機質な文章に、人の心は動きません。私たちが読みたいのは、血の通った人間が書いた、温かい文章のはずです。
キーワードは、あくまで自然な日本語の文章の中に、そっと溶け込ませるのが理想です。詰め込みたい気持ちは痛いほど分かりますが、最も重要だと思うキーワードを1つか2つに絞り、読者がスムーズに読める文章を最優先に考えましょう。近年のGoogleは、キーワードの数よりも、読者の検索意図にどれだけ応えられているかを重視しています。読者に評価されないタイトルが、検索エンジンに高く評価されることは決してありません。
【こんな記事で特に注意!】
SEOを学び始めたばかりの人が陥りがちな罠。キーワードは「入れる」のではなく「溶け込ませる」という意識を持ちましょう。
パターン10:結局何が言いたいか不明な「長すぎる」タイトル
【ダサい例】
私がブログを始めた当初に知りたかった、初心者が絶対にやってはいけないタイトルの付け方と読まれるためのコツを全部教えます
【改善例A(核心を突く)】
【初心者向け】読まれるブログタイトルのコツは「先にNG例を知ること」だった
【改善例B(要点を絞る)】
ブログ初心者がやりがちな「NGタイトル」5選と、読まれるための改善策
【解説】
読者に多くの価値を届けたいという親切心から、ついタイトルに情報を詰め込みすぎてしまう。その気持ち、痛いほどよく分かります。しかし、タイトルが長すぎると、スマートフォンの検索結果では後半部分が「…」と切れてしまい、本当に伝えたい核心部分が読者に届きません。
タイトルは、映画のキャッチコピーのようなものです。「数々の困難を乗り越え、仲間との絆を深め、最後に巨悪を討つ感動の物語」と説明するのではなく、「愛する人を守るため、男は伝説の剣を抜いた」と、最も核心を突く一言で、観客(読者)の心を掴む必要があります。伝えたいことは記事の本文でたっぷりと語るとして、タイトルでは最も重要なメッセージを、32文字前後を目安に、簡潔にまとめることを意識してください。
【こんな記事で特に注意!】
網羅性の高いまとめ記事や、渾身の長文記事。伝えたいことが多い時ほど、タイトルはシンプルに研ぎ澄ます必要があります。
【応用編】「ダサい」の壁を越え、思わずクリックされる「神タイトル」の法則

さて、ここまで「ダサいタイトル」を避けるための10のNGパターンを見てきました。これらを避けるだけでも、あなたのブログのクリック率は大きく改善されるはずです。しかし、ここからはさらに一歩進んで、競合記事の中から頭一つ抜け出し、読者の心を鷲掴みにする「神タイトル」を作るための、より応用的な5つの法則をご紹介します。
法則1:ギャップ法(常識の逆を突く)
人は、自分の信じている常識や当たり前が覆されることに、強い興味を引かれます。「え、どういうこと?」と思わせることができれば、クリックされる確率は飛躍的に高まります。
-
例1: 「ブログは毎日更新しなさい」→ 「成果を出したいなら、ブログは毎日更新してはいけない」
-
例2: 「たくさん本を読もう」→ 「読書量を増やしても、思考力は伸びない。たった1つの正しい読書法とは」
-
例3: 「節約してお金を貯めよう」→ 「普通の人がお金持ちになるには、節約ではなく〇〇を増やすしかない」
【使い方のコツ】
その業界やジャンルの「当たり前」とされていることを疑ってみましょう。ただし、単に逆を言うだけでなく、記事の中で読者が納得できるだけの、しっかりとした根拠を示すことが絶対条件です。
法則2:権威性法(専門家や実績を示す)
人は、権威のある人や信頼できる人の情報に強く惹かれます。「誰が言っているか」は、情報そのものと同じくらい重要なのです。
-
例1: 「痩せる方法」→ 「年間500人を指導するパーソナルトレーナーが教える、リバウンドしない食事法」
-
例2: 「美味しいコーヒーの淹れ方」→ 「バリスタ世界チャンピオンが明かす、いつもの豆が高級店の味になる秘訣」
-
例3: 「ブログタイトルの付け方」→ 「元Google社員が語る、SEOの本質とクリックされるタイトルの関係性」
【使い方のコツ】
あなた自身に権威性(資格、経歴、実績など)があれば、それを積極的に使いましょう。もしなくても、「〇〇の専門家に取材しました」「〇〇の論文によると」といった形で、情報の信頼性を補強することが可能です。
法則3:緊急性・限定性法(今すぐ行動を促す)
人は、「今しかない」「自分だけ」という言葉に弱い生き物です。機会損失を恐れる心理(プロスペクト理論)をくすぐることで、クリックを後押しします。
-
例1: 「セール情報」→ 「【本日23:59まで】Amazonタイムセール祭りで本当に買うべき、隠れた名品リスト」
-
例2: 「〇〇の始め方」→ 「知らないと損する。2025年から始める〇〇が有利な理由」
-
例3: 「お得な情報」→ 「【30代限定】あなたが申請するだけでもらえる、意外と知られていない給付金一覧」
【使い方のコツ】
多用すると効果が薄れるため、ここぞという時に使いましょう。「限定」という言葉を使う際は、ターゲットを明確に絞ることで、「私のことだ!」と強く感じさせることができます。
法則4:五感を刺激する言葉を使う

読者の脳内スクリーンに、映像や音、匂いが浮かぶような具体的な言葉を使うことで、タイトルは一気に生命感を帯びます。
-
例1: 「美味しいパンの紹介」→ 「一口かじればバターがじゅわっ。焼きたてクロワッサンが絶品のパン屋さん5選」
-
例2: 「おすすめのマットレス」→ 「雲の上で眠るような寝心地。腰痛持ちの私が感動した、魔法のマットレス」
-
例3: 「静かな場所」→ 「しとしとと降る雨音だけが響く。時間を忘れる、古民家ブックカフェのすすめ」
【使い方のコツ】
抽象的な「すごい」「良い」といった言葉を、具体的な五感表現に置き換えられないか考えてみましょう。特に、グルメ、旅行、インテリアなどのジャンルで絶大な効果を発揮します。
法則5:読者に問いかける
一方的に情報を提示するのではなく、読者に問いかけることで、タイトルは「自分事」に変わります。読者はその問いに答えるために、思わず記事を読み進めたくなります。
-
例1: 「〇〇は危険です」→ 「あなたのその習慣、実は〇〇のリスクを高めているかもしれません」
-
例2: 「ブログで稼ぐ方法」→ 「あなたのブログが稼げない本当の理由、知りたくありませんか?」
-
例3: 「整理整頓のコツ」→ 「『いつか使うかも』が口癖のあなたへ。人生が変わる、たった1つの片付けルール」
【使い方のコツ】
読者が「ドキッ」とするような、核心を突く問いかけを意識しましょう。読者が無意識に抱えている悩みや課題を言語化してあげることで、強い共感と信頼を生み出します。
なぜそのタイトルは「ダサい」のか?読者が無意識に避ける心理

ここまで10のNGパターンと5つの応用法則を見てきましたが、根底に流れる原理は同じです。私たちが「ダサい」と感じるタイトルには、読者のクリックを妨げる共通の心理的な壁が存在します。その正体を、もう少しだけ深く掘り下げてみましょう。
理由1:情報の信頼性が低そうに見えるから
過剰な装飾や古い表現、キーワードの羅列は、読者に「この記事は中身が薄いプロモーション記事かもしれない」「書き手の情報が古そうだ」という無意識の警戒心を生みます。これは心理学でいう「ハロー効果」の一種で、一部分の悪い印象(タイトル)が、全体(記事の中身)の評価にまで影響を与えてしまう現象です。読者は貴重な時間を無駄にしたくないため、少しでも怪しい、信頼できないと感じたタイトルは、たとえ中身が素晴らしくても、本能的に避けてしまうのです。
理由2:読むメリット(ベネフィット)が1秒で伝わらないから
読者は非常に忙しく、検索結果の画面をスクロールしながら、タイトルを一目見た瞬間に「自分に関係あるか」「読む価値があるか」を超高速で判断しています。ここで重要なのが、「機能」と「ベネフィット」の違いです。例えば「高性能なドリル」は機能ですが、「誰でも簡単に、美しい穴が開けられる」はベネフィットです。日記風のタイトルや専門用語だらけのタイトルは、この「ベネフィット」が欠けています。読者がタイトルに求めているのは、この記事を読むことで得られる「自分の未来の、ポジティブな変化(ベネフィット)」なのです。それが1秒で伝わらないタイトルは、残念ながら存在しないのと同じなのです。
理由3:書き手のレベルが低そうに見えるから
平凡なタイトルや、どこかで見たようなテンプレそのままのタイトルは、「この書き手は初心者だな」「ありきたりな情報しかなさそうだ」と判断されてしまいます。結果、もっと専門的で、独自の視点を持っていそうな魅力的なタイトルの記事に読者は流れていってしまいます。タイトルは、あなたがどれだけ読者のことを深く考え、悩みに寄り添おうとしているかを示す「おもてなしの心」の表れです。そのおもてなしの心が感じられないタイトルは、読者から選ばれることはないでしょう。
もう迷わない!「ダサいタイトル」を卒業するための最終チェックリスト

今後、あなたがタイトルを付け終えた後に、必ず確認してほしい「お守り」のようなチェックリストです。このひと手間が、あなたの記事の未来を大きく変えます。各項目について、なぜ重要なのかも併せて解説します。
-
[ ] このタイトルで、ターゲット読者は「私のことだ!」と気づくか?
-
なぜ重要か: 漠然と「皆さんへ」と呼びかけるよりも、「〇〇で悩んでいるあなたへ」と呼びかける方が、心に深く突き刺さるからです。読者は、自分専用のメッセージだと感じた時に、初めて記事に興味を持ちます。
-
-
[ ] 読者が得られるメリットや、解決できる悩みが含まれているか?
-
なぜ重要か: 読者は、あなたの記事を読むという「時間」を投資します。その見返りとして何が得られるのか(ベネフィット)が明確でなければ、誰も投資してくれません。
-
-
[ ] 具体的な数字やパワーワード(簡単、限定など)で興味を引けているか?
-
なぜ重要か: 「痩せる方法」より「3ヶ月で10kg痩せた方法」の方が、具体的で信頼性が高く、興味を引かれます。数字は、タイトルの説得力を飛躍的に高めるスパイスです。
-
-
[ ] 2025年の今、この表現は古臭い・ダサいと思われないか?
-
なぜ重要か: 言葉にも鮮度があります。古い言葉遣いは、情報そのものの鮮度も疑わせてしまいます。一度、友人や家族にタイトルを見せて、客観的な意見をもらうのも非常に有効です。
-
-
[ ] 他の競合記事タイトルの中に埋もれない、少しの独自性はあるか?
-
なぜ重要か: 検索結果は、競合との相対評価の世界です。全く同じようなタイトルが並んでいれば、ドメインの強い大手サイトが勝ってしまいます。あなた自身の体験や独自の視点という「少しのズラし」が、弱者が強者に勝つための唯一の戦略です。
-
-
[ ] スマホの検索結果で表示される32文字以内に、最も伝えたいことは入っているか?
-
なぜ重要か: ほとんどの読者はスマートフォンで検索しています。後半に重要な言葉を置いても、途中で切れてしまい読まれません。最も伝えたいキーワードやベネフィットは、必ずタイトルの前半に配置する癖をつけましょう。
-
まとめ

ブログタイトルの「ダサさ」は、生まれ持ったセンスの問題ではありません。それは、読者の心理と現代の基準を知っているかどうかの「知識」の問題です。かつて、看板も出さずに素晴らしい料理を作り続けていた私のように、あなたもほんの少しの知識で、劇的に変わることができます。
この記事を閉じた瞬間から、あなたはもうタイトル決めに悩むことはありません。なぜなら、あなたは「ダサいタイトル」を避けるための明確な地図と、魅力的なタイトルを作るための羅針盤を手に入れたからです。
-
ダサいタイトルはセンスではなく、10個のNGパターンという「知識」で回避できる
-
読者はタイトルから「信頼性」「メリット」「書き手のレベル」を1秒で見抜いている
-
応用編の5つの法則を使えば、さらに読者の心を掴む「神タイトル」が作れる
-
最後のチェックリストは、あなたの記事を読者に届けるための「お守り」になる
-
まずは過去記事を1つ、この記事を参考にリライトすることから始めてみる
その小さな一歩が、あなたのブログを、そしてあなたの「書き手」としての人生を、大きく変えるきっかけになることを、心から信じています。
